首記のとおり。去年はカメラ故障につき動画が残せなかったので、統計で大まかな流れをつかむことにしたさ。
(そこっ!今更とかいわないっ!?)
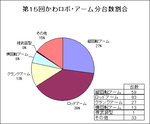
意外とロッドアーム多かったんですな。

ただ、山を超えて攻撃できるロッドアーム(大型+中型展開)は11台ですか...全体の5%と考えると、意外と少ないね。
やはり380制限のおかげで、ロングリーチのアームが作りにくくなっているってことなんじゃろか?
また、分類してて思ったのが、決勝で活躍してるロボって、回転系だと大型化する傾向にあるんじゃね(やはり)
小型機は数こそ多いものの、上位で見たロボ自体は少ない....いわゆる発展途上といったところか。
たまーに小型で出力重視なロボとかいるけどさ。燐以外にもね。
ただ、そういった無理して高い性能引き出せているのは身内ばかりで、
一般的にはサイズ拡大化の傾向だろうな。
そんな大型を安定して数多く倒すためには、ロッドメインの機体としてはそれなりにリーチを伸ばす必要があるわけで....

<リーチ、約400~600(カウンターステア付)>
方向性としては間違ってないんかな。
